今ダイバーの中での人気生物であるウミウシ。
今回はそのウミウシについての簡単な知識と、種類について解説していきたいと思います。
ウミウシとは
貝殻が縮小したり体内に埋没、消失などした種の総称です。
名前の由来
頭に2本の触覚をもち、牛のように見える事からウミウシ(海牛)と呼ばれるようになりました。
名前はニックネーム??

実はウミウシという名前は分類学的には正式名称ではないのです。
正式名称ではないという事は、ウミウシという定義が存在していないという事です。
そこにウミウシブームの影響も重なり、ウミウシは昔より広い範囲の生き物を指すようになりました。
なので牛のような触覚がない生き物もウミウシの仲間として図鑑に載っています。
大きさ

種類によってかなりの差があり、1mmに満たないものから60cm程まで成長する種もいます。
購入

価格は1500〜2500円程です。
ペットショップ、ネットどちらでも手に入ります。
種類
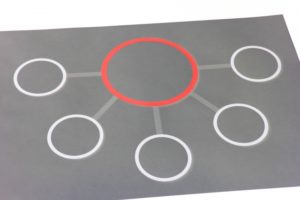
先程お話した通り定義がないので正確ではありませんが3000種類以上いると言われています。
そして『〜亜種』や『〜sp』など、まだ名前がついていない種が多数存在している為、今後数が増えることも予想されます。
ここから先は5種の目について解説していきます。
裸鰓目
皆さんが1番目にしているのは、きっと裸鰓目でしょう。
この目にいるウミウシは例外なく貝殻を持っていません。
そしてかなりの種類が所属しているので、4つのグループに分類分けされています。
裸鰓目・ドーリス亜目
ドーリス亜目に分類される種類のほとんどが2本の触覚と花びらのような鰓を持っています。
THEウミウシの形といえますね。
代表的なウミウシだと
ウデフリツノザヤウミウシ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
アオウミウシ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
シラユキウミウシ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
などがいます。
裸鰓目・ミノウミウシ亜目
ミノウミウシ亜目の最大の特徴は背中部分にあるトゲトゲの突起でしょう。
ある程度例外はいますが、この突起が見られるウミウシのほとんどはミノウミウシ亜目に属しています。
この突起はミノと呼ばれています。
おそらく昔雪よけの為に羽織っていた簑からきている名前でしょう。
毒成分はイソギンチャクなどウミウシが餌にしている生き物から蓄えています。
代表的なウミウシだと
アオミノウミウシ
アオミノウミウシ
(猛毒の「カツオノエボシ」(別名:電気クラゲ)を主食にしている) pic.twitter.com/e77AxUAJt4— 珍獣図鑑 (@exchangtiklfbm1) May 22, 2020
アカエラミノウミウシ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
などがいます。
裸鰓目・スギノハウミウシ亜目
ミノウミウシと同じように背中部分に突起があるのが特徴です。
ミノウミウシとの見分け方は触覚部分を見てください。
スギノハウミウシ類は触覚の付け根が鞘の様な形状になっているので、触覚さえ見ればすぐに違いに気がつく事が出来ると思います。
代表的なウミウシだと
シロハナガサウミウシ
がいます。
裸鰓目・タテジマウミウシ亜目
触覚のヒダが縦に入るオトメウミウシ系と、ミノウミウシの様に背中に突起が沢山あるショウジョウウミウシ系の2組みによって成り立っています。
同じグループなのに全然形が似ていない珍しいグループです。
なぜ同グループなのかは、体内のつくりが他のグループと異なるからです。
ややこしいグループですが種類があまりいないので、全種覚えてしまう事が手取り早い見分け方法かもしれませんね!
代表的なウミウシは
ハスエラタテジマウミウシ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
トゲトゲウミウシ
がいます。
頭楯目
頭楯目は貝殻を持つ種が多く、頭部に触覚が無いのが特徴です。
名前の通り、頭が楯の様な形をしている種類がほとんどです。
頭部の形状を活かして砂をかき分けて進んだり、潜って隠れるという行動をします。
頭の形が楯になっていない種類でこの目に所属しているのは、ウミコチョウの仲間でしょうか。
代表的なウミウシだと
ベニシボリ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ムラサキウミコチョウ
ムラサキウミコチョウ☆
location:和歌山
撮影日:2020.2#撮るからには最高の1枚を#海 #風景 #景色 #マクロ #ワイド#ダイビング #和歌山 #田辺https://t.co/uieATXo8GT pic.twitter.com/JBlqM7BXTR— シン (@tshin_photo) February 15, 2020
などがいます。
背楯目
背楯目は先程の頭楯目と違い、背中に大きな楯があるのが特徴です。
また転石の下に隠れる事が多いのも特徴と言えるでしょう。
地味な種類が多いので、あまり人気が無いのが残念です。
代表的なウミウシだと
ヒトエガイ
ヒトエガイ pic.twitter.com/AMW9HPzfFf
— さかなくん28号 (@sakanakun2000) April 3, 2014
がいます。
無楯目
無楯目=アメフラシと覚えておくと簡単です。
実際に別名アメフラシ目と呼ばれています。
「楯が無い」というところから無楯目という名前がついていますが、実際には背中部分のひらひらの間に平らな貝殻があります。
代表的なものは
もちろんアメフラシでしょう。

嚢舌目
嚢舌目の特徴は口部分にあり、使い捨ての鋭い歯舌と切れ味の悪くなった歯舌を収納する袋を持っています。
海藻に穴を開けて中身を効率よく吸い出す為、この様な作りになっています。
特徴が体内にあるので、やや見分けにくいのがこのグループです。
見分ける為には下記の3種類を覚えて、「似ている様なら嚢舌目」といった見分け方が有効的だと思います。
スイートジェリーミドリガイ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
背中のヒダの様な物が特徴です。
ミドリアマモウミウシ
ミドリアマモウミウシ
Placida dendriticaLocation: 波板海岸
Size: 2mm
Depth: 5mビッシリついてる緑藻もある
緑藻が消えたらどうなるんだろう#ウミウシ #今日のウミウシ #… https://t.co/iBVyvCLadT pic.twitter.com/MHqsXvcNTo— とと (@totoslug) July 22, 2017
ミノウミウシ亜目と似ていますが、見分けポイントは口部分に触覚があるかどうかです。
嚢舌目のウミウシには口触覚がありません。
ユリヤガイ
2枚貝を持つ変なウミウシ、ユリヤガイ #ウミウシ #毎日ウミウシを紹介してみる #水中写真
Found at http://t.co/h1TtCtzHsp pic.twitter.com/asgomZn1KJ
— 世界のウミウシ (@seaslug_world) August 8, 2014
背中部分に貝を持っています。
ベニシボリなどと違い、体が入る様な大きい貝です。
まとめ
いかがでしたか?
今回はウミウシについて簡単に解説してみました。
まだまだお伝えしたい生態が沢山ありますが今回はこの辺で!
磯採取などでも見かける事ができますので、宝探し感覚で探してみてくださいね!
最後までご愛読ありがとうございました。



コメント