こんにちは!
今回はハゼの中でも一際目立つ色合いで人気があるギンガハゼを紹介していきたいと思います。
ギンガハゼと言えばエビと「共生」することでも有名です。
飼育方法はもちろん、共生についても詳しく解説していきたいと思います。
ぜひ最後まで読んでいって下さいね。
ギンガハゼとは

ギンガハゼはスズキ目ハゼ科に属する海水魚です。
アンダマン海や中〜西部の太平洋に分布しています。
以前著者がタイでダイビング際はかなりの数のギンガハゼを見つけました。
やはり多い地域には沢山いるんですね。
ダイバーからもアクアリストからも人気があるのは、やはり色合いが良いからですね!
名前の由来
ギンガハゼ。小さい子の方が大きい子より黄色が綺麗です。撮影場所はタオ島のダイブサイトのツインズ。ここのハゼ達はダイバー慣れしていて、かなり近くまで寄る事ができます。(α7RIII/FE90mmf2.8macro)#diving #水中撮影 #タオ島 #ダイビング #ギンガハゼ #水中マクロ pic.twitter.com/bh9FNZseMz
— Nabejizo (@pssiam) September 25, 2019
さてギンガハゼの名前に注目してみましょう。
ギンガを漢字にすると「銀河」になりますようね。
そうなんです、青い斑点模様が銀河の様に見えることからギンガハゼと呼ばれるようになったそうです。
これまで色々な魚の解説を書いてきましたが、名前の由来がギンガハゼほどロマンチックなお魚はいなかったです!
モテたい男子諸君は自宅でギンガハゼを飼育して、女の子が遊びにきた際に小ネタとして紹介してみて下さい。
きっとその子とは上手くいくはずです・・・・(笑)
大きさ
#上皇陛下のお誕生日なのでハゼの画像を貼る2020
ギンガハゼ pic.twitter.com/JKVOPomxO7— ニゴモロコ (@nigomoroko) December 23, 2020
さてしっかり切り替えて大きさをみていきましょう。
ギンガハゼは成長すると8cm前後まで大きくなります。
大きい個体だと10cmになる事もあるので比較的大きめのハゼと言えるでしょう。
寿命

ギンガハゼの平均寿命は3〜5年とされています。
飼育下では水槽の状態や餌の量などの影響を受けて、寿命は前後する様です。
しっかりとした設備と管理で迎え入れてあげて、長生きさせてあげて下さいね。
性格
ギンガハゼ。若い子は、目がぱっちり!で黄色も綺麗です。#ダイビング #タオ島 #水中撮影 #水中マクロ #タイランド #ギンガハゼ #ハゼ pic.twitter.com/iupwrtWHyt
— Nabejizo (@pssiam) October 14, 2019
ギンガハゼの性格は比較的温厚と言えます。
基本的に他魚を襲ったり追いかけ回したりする事はありませんが、巣穴の近くに寄ってくる魚に対しては追い払う素振りをみせます。
購入

ギンガハゼはネット通販もしくはアクアリウムショップで購入することができます。
価格としては一匹当たり1500〜2000円前後が相場と言えるでしょう。
人気のハゼではありますが取り扱っていないお店も多いのでネット購入の方が、手に入れやすいと思います。
またギンガハゼは丈夫な事でも有名なので、運送時のダメージも心配になりません。
大きさが分からないのがネックではありますが総合的にはネット購入がおすすめです。
カラー
ギンガハゼといえば綺麗な黄色の体を思い浮かべがちですが、実は黄色ではなくグレーの個体もいるのです。
ギンガハゼ
緑の絨毯
うみの杜水族館 pic.twitter.com/Qs9w073Gzy
— 片想い患い中 (@moon1868) September 19, 2019
もちろん黄色の方が人気があり、販売されている個体の9割以上が黄色ですがごく稀にグレーの個体が販売されている事もあります。
派手さはありませんがグレーはグレーなりの良さがあるので、珍しいもの好きの方はぜひ飼育してみてはいかがでしょうか?
エビとの共生
冒頭でも少し触れましたがギンガハゼはエビと共生する魚です。
コシジロ&ギンガハゼ
ハゼは和みます~ pic.twitter.com/ny3Dy82BYl— ネこ(ФωФ) (@URANI14210940) July 18, 2019
共生には様々な種類があり、ギンガハゼとエビはお互いに利益のある「相利共生」です。
ギンガハゼは危険が迫った時に巣穴に避難させてもらうかわりに、普段は周囲の見張りをしているのです。
エビは巣穴を提供するかわりに、危険が迫った際にギンガハゼからサインをもらっているのです。
共生相手として1番相性がいいのはニシキテッポウエビです。
他にもランドールズピストルシュリンプなども共生が可能です。
ぜひギンガハゼ飼育の際は共生する様子を観察しましょう!
ギンガハゼを飼育してみよう
ギンガハゼの基本情報がわかったら飼育方法について学んでいきましょう!
飼育アイテムを揃えよう!

・水槽
・ろ過装置
・ヒーター
・クーラー
・エアー用品
・底砂
・エサ
・ライブロック
上記のアイテムは他の海水魚の飼育でも使用する基本アイテムです。
基本的なアイテムがあれば問題なく飼育する事が出来るのでチャレンジしやすい種と言えますね。
海水水槽の詳しい立ち上げ方についてはこちらをご覧下さい。

水槽サイズ

ギンガハゼを飼育する際は30cm以上の水槽を準備しましょう。
ギンガハゼはほとんど泳ぎ回らずに、巣穴周辺をウロウロしているくらいなので小さな水槽でも飼育が可能なのです。
他の魚と混泳させる場合には45cm以上の水槽を準備しましょう!
30cmも45cmも水槽としては小型なので水質悪化のスピードが早いので、こまめな手入れが必要です。
ギンガハゼは丈夫な種ではありますが油断せずに飼育しましょう。
小型水槽での飼育が心配な方は以下の記事を参考にして下さい。

水温
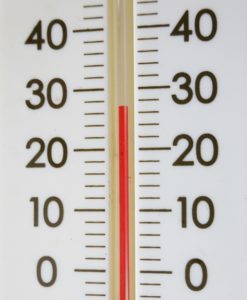
ギンガハゼを飼育する場合には24〜25度をキープするようにしましょう。
飼育可能な水温としては21〜28度ですが、分布からもわかるように特に低水温を苦手としています。
水温が下がると動きが悪くなり、餌の食いつきが悪くなるので注意しましょう。
もちろん高温すぎるのもよくないので、ヒーターやクーラーを設置して一定をキープしましょう!
混泳

混泳については性格のコーナーでも少し触れましたが、巣穴から遠征してまで攻撃したりすることは無いので中層を泳ぐ魚の大半とは混泳が可能です。
しかし生活圏の被る同種や他種のハゼには威嚇や追い払う、喧嘩などの動きをすることが多いです。
その為120cmなどの大きな水槽でない限りは低層を泳ぐ魚との混泳は避けるのが無難でしょう。
混泳相手が気が荒かったり、肉食の場合には標的になりかねないので混泳させないようにしましょう。
エサ
ギンガハゼは人工エサも生エサもどちらも食べてくれます。

ギンガハゼの場合、エサの種類ではなくしっかりとエサが行き渡るかどうかが重要です。
ギンガハゼはエサを求めて泳ぐというよりか、流れてきたエサを食べるというタイプのため近くにエサが行かないと食べてくれません。
なので沈殿性のエサであることが大事です。
またスズメダイなどエサへの反応が良い種と混泳している場合には沈むまでに全て食べられてしまう可能性もあります。
その際は多めにエサを与えるか、スポイトを使って意図的に近くに落としてあげると良いでしょう。
死因としてはエサが行き渡らずに餓死してしまうパターンが多いので気をつけましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は派手な色合いと「共生」という行動が観察できるギンガハゼについて解説してきました。
色合いと共生以外にも小さな水槽でも飼育できる点や丈夫な点など非常に飼育にチャレンジしやすい点が多いです。
飼育する種に悩んだらギンガハゼにチャレンジしてみて下さいね!
最後までご愛読いただきありがとうございました。



コメント